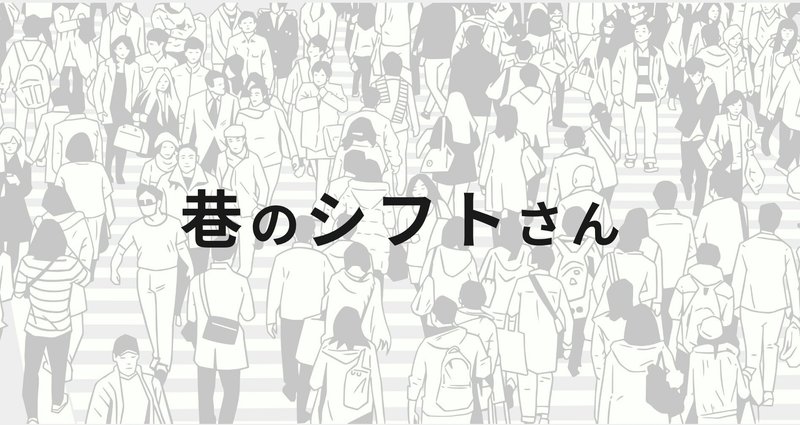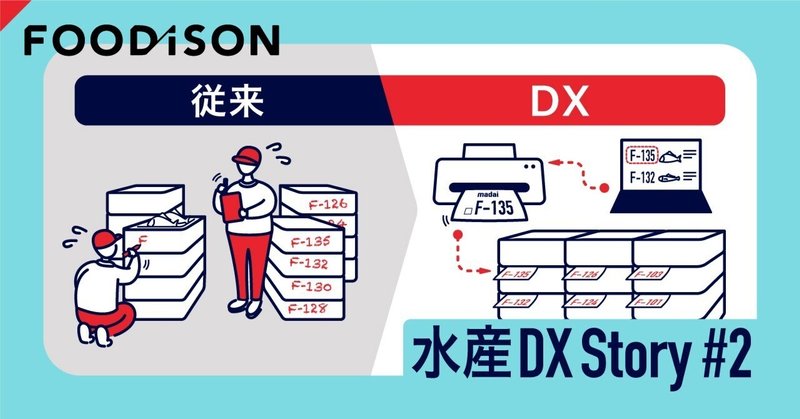記事一覧

【雨風太陽 社員インタビュー】旅行会社から"本当にやりたいこと"を求めてジョイン!ポケマルおやこ地方留学を通して、他にはない価値を提供していく—人流創出部・髙嵜令奈
ポケマルおやこ地方留学は、全国各地の生産者さんのもとで自然や食について学ぶ親子向けプログラムです。参加者の皆さんからは「生産者さんが出品する商品を購入したい」「生産者さんにまた会いに行きたい」などの感想を多くいただき、単なる旅行には留まらない、生産者と消費者を繋ぐ雨風太陽らしい価値を提供しています。 本事業のミッションに共感をし、雨風太陽にジョインした人流創出部の高嵜。運営側から見たポケマルおやこ地方留学の価値、本事業を通して伝えていきたい思いなどを聞いてみました。 —前

野菜で笑顔を育みたい。10年越しで実現した「ヤサイな仲間たちファーム」に込められた想い_kewpie standard : FILE 04
キユーピーグループはこれまでさまざまな野菜の食べ方の提案や商品開発を通じて、野菜摂取の促進に取り組んできました。2022年5月、埼玉県深谷市にオープンした複合施設「深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム」(以下、ヤサイな仲間たちファーム)もそのひとつです。 施設内には、野菜の収穫体験ができる「体験農園」や、野菜や加工品を販売する「マルシェ」があり、大人から子どもまで、野菜の魅力を多角的に楽しむことができます。地域内外から注目を集めるヤサイな仲間たちファームですが、実は構想か